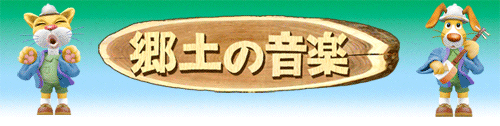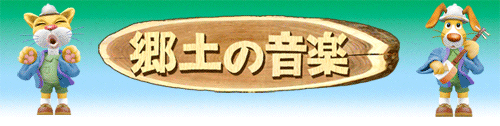新潟〔にいがた〕県の佐渡島〔さどしま・さどがしま〕に伝わる鬼太鼓は,その年の豊作〔ほうさく〕や大漁,家内安全や商売繁盛〔しょうばいはんじょう〕などを祈〔いの〕りながら家々の厄〔やく〕をはらうための神事です。
現在〔げんざい〕は,100をこえる保存会〔ほぞんかい〕によって受けつがれており,それぞれの集落に伝わっている踊〔おど〕りの型や登場するものたちは実にさまざまです。中には,鬼〔おに〕役の人たちが早朝から深夜までかけて集落じゅうの家々を回り,最後に集落の中のお社〔やしろ〕に踊りを奉納〔ほうのう〕するまで交替〔こうたい〕で踊〔おど〕り続けるところもあります。
各集落で独自〔どくじ〕のスタイルをもつ鬼太鼓ですが,「相川系〔あいかわけい〕」「国仲系〔くになかけい〕」「前浜系〔まえはまけい〕」の三つの系統〔けいとう〕に大きく分けられます。相川系は,ほかの二つに比〔くら〕べて鬼の動きはあまり激〔はげ〕しくありません。鬼はほとんど踊らず,その周りを「豆まき」という翁〔おきな〕が踊ることがあります。それに対して国仲系は,激しい動きと見ばえのする踊りが特徴〔とくちょう〕です。場所によっては鬼に加えて,獅子〔しし〕が登場することもあります。前浜系は,太鼓〔たいこ〕のほかに笛が用いられるところに特徴があります。
このように,それぞれの集落に密着〔みっちゃく〕したものが,今も受けつがれているという点は,鬼太鼓の大きな魅力〔みりょく〕でしょう。太鼓のリズムもさまざまですが,鬼が激しく舞〔ま〕いながら太鼓を打ち鳴らす「しだら打ち」と呼〔よ〕ばれる打ち方は,見るものを圧倒〔あっとう〕する迫力〔はくりょく〕があります。
|